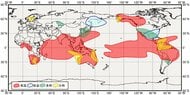2024年の6月は台風の発生がなく、これは2016年以来、8年ぶりのことだ。ただ、台風の卵である熱帯低気圧が、例年だと7月以降、本格的に日本の南で発生し始める。このため、台風への備えが必要になってくる。
2024年 台風の見通しは?
2024年の台風の気になる見通しだが、日本気象協会が予想した発生数は、7月から8月はいつもの年と同じくらいか少なく、9月から10月はいつもの年と同じくらいだ。
台風予想発生数(個)
7月:1~4
8月:3~6
9月:4~6
10月:3~5
また、本土への接近数は、7月はいつもの年と同じくらいか少なく、8月から10月はいつもの年と同じくらいか多い見通しである。
台風予想接近数(個)
7月:0~2
8月:2~4
9月:1~3
10月:1~2
予報円の大きさ=台風の大きさではない!!
台風が日本に近づくと、天気予報やニュースなどで台風情報が取り上げられる。そこには、台風の現在の位置や勢力、進行方向と速度、予想される進路などが示される。
特に目立つのは台風の予想進路を示す円であろう。この台風進路図の中にある円は、予報円と呼ばれる。台風の中心がその範囲内(円)のどこかに入る確率が高い(70%以上)ことを示す。

この予報円が大きいほど、台風がどこに進むかが定まっておらず、今後の進路や速度がまだ不確実であるということだ。
また、自分が住んでいる地域や、離れて住んでいる家族や親戚などの地域に予報円が重なっていなくても、予報が変わる可能性もあるので、最新の台風情報をこまめに確認しよう。
台風の番号とアジア名
台風には、1月1日以降の発生順に番号が付けられる(例:台風1号、台風2号)。さらに、アジア名も付けられている。これは日本を含むアジア・太平洋地域の14カ国等によって組織されている台風委員会にて、それぞれの国や地域が名前を提案し決められている。
これは、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めることも目的の1つで、花や鳥、果物やお菓子など様々な名前が付けられている。
140個のアジア名のうち、日本からは星座名に由来する名前10個を提案しているそうだ。ちなみに、2024年は5月に台風第2号まで発生しており、台風第2号のアジア名は「Maliksi(マリクシ)」。この名前はフィリピンが提案したもので、「速い」を意味する。
台風前の備え
ニュースやインターネットなどで台風が近づくという情報を得たら、台風によるライフラインへの影響を考慮して、事前の備えをしよう。
数日間分の食料や水、常備薬、懐中電灯、電池などを用意しておく。日頃から食料や水などを多めに買い置きしておき、ローリングストック(買い置きした食料や水を古いものから食べたり飲んだりして消費し、買い足しをするやり方)を実施しておくのもおすすめだ。

しばらくはお風呂に入れなくなることもあるので、使い捨ての体拭きやドライシャンプーなどを用意しておくと良いかもしれない。また停電に備えて、スマートフォンなどの充電をしておこう。お風呂の残り湯は、トイレを流すなどの生活用水として取っておくのも良さそうである。
普段はキャッシュレス決済に慣れている人も多いかと思うが、停電になると、電子マネーなどが使えなくなる場合もある。小銭や紙幣も必ず用意しておくと安心だ。

まだ台風が日本に近づいていない明るい時間帯に家の周りを確認しておく。窓ガラスを養生テープや板などで補強し、風で飛びやすいもの(植木鉢、自転車など)は屋内に移動させる。
ハザードマップなどで自宅周辺にどのようなリスクがあるのか確認しておこう。自宅が土砂災害警戒区域に入っておらず、近くに山がないのであれば避難のために屋外に出るリスクの方が高くなる。災害の危険性がなく安全が確保されているのであれば、在宅避難も選択肢の1つだろう。

もし、自宅周辺が土砂災害や浸水害のリスクのある地域であれば、近くの避難場所や避難経路を確認し、家族や同居人がいる場合は連絡方法などを話し合い、緊急時に備えておこう。
台風の接近・上陸時の注意
台風の接近や上陸にともなって起こり得る災害としては、暴風、大雨、洪水、浸水、高波、高潮など多岐にわたる。

暴風や大雨のときには、家の窓やドアをしっかりと閉める。土砂災害などの危険がある場所には近づかないことが大切である。家の中にいても危険そうな場所は避ける。家の近くに山や崖など、崩れる恐れのある斜面がある場合は、斜面から離れた部屋に避難するようにしよう。
また、強い風で飛ばされた物によって電線が損傷したり、大雨による土砂崩れで電柱・電線が損傷したりすることによって停電になる場合がある。停電が発生したら、電気のブレーカーを落としておく。電気の復旧と共にショートし、火災になるのを防ぐためである。避難する際にも、ブレーカーを落としておこう。

洪水や浸水のときは、河川や用水路からは離れて高い場所へ避難する。水が流れ込む危険があるため、地下室や地下街、地下駐車場などには入らない。自宅での対策としては、大切な家具や家電などを高い場所に移動させておくのも良い。
高波や高潮も台風に伴って起こる。海岸や堤防に絶対に近づかない。もし、海水浴や釣りを予定していても非常に危険なので中止する。台風の中心から離れていても、海では高波やうねりが来たり、高潮によって一気に水位が上がったりするおそれがあるので、例え晴れていても油断禁物である。

特に重要なことは、最新の情報を確認することだ。市町村から避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝えられるので、速やかに従うことである。
高齢者の避難のタイミングに関しては、自治体が「高齢者等避難」の情報を出すことになっている。大雨・洪水警報や川の氾濫警戒情報が発表されるような状況である。発表されたら、高齢者や体の不自由な人などは避難を始め、このほかの人も避難場所の確認や持ち出す物の準備を進め、危険を感じたら自主的な避難を始めることだ。
台風後に気をつけること
台風が去って天気が回復してきても、外出前には倒木や電線の切断、浸水被害などの危険がないか慎重に確認する。水路や河川の水位がまだ高い可能性があるため、川などには近づかない。

家電を使用する前に漏電や感電の危険がないか確認する。飲料水などの確保のため、水道水が安全かどうかを確認し、必要なら煮沸する。健康管理も大切であり、感染症予防のために手洗いや消毒を徹底する。
また、台風が通り過ぎたり、台風が温帯低気圧に変わったりしても、警報や注意報が解除されるまでは油断してはいけない。台風が温帯低気圧に変わるときに暴風域が急速に広がることもあることもあるので気をつけよう。台風が接近する前には早めの備え、そして台風が離れた後も最新の情報をきちんと確認し、安全確保に努めることが大切である。
【執筆:日本気象協会】