コロナ禍では、各国の文化芸術に対する想いが顕在化した。ドイツ政府は文化芸術を「生命の維持に必要不可欠」と発表した一方、日本では「不要不急」のものとして支援が遅れた。
日本の文化芸術は、アフターコロナでどうなるのか?演劇界を代表する劇作家・演出家の平田オリザさんに聞いた。平田さんは、兵庫県豊岡市で来年4月に開校する、国際観光芸術専門職大学(仮称)の学長に就任される予定だ。
日本に演劇の学び場がない恥ずかしさ
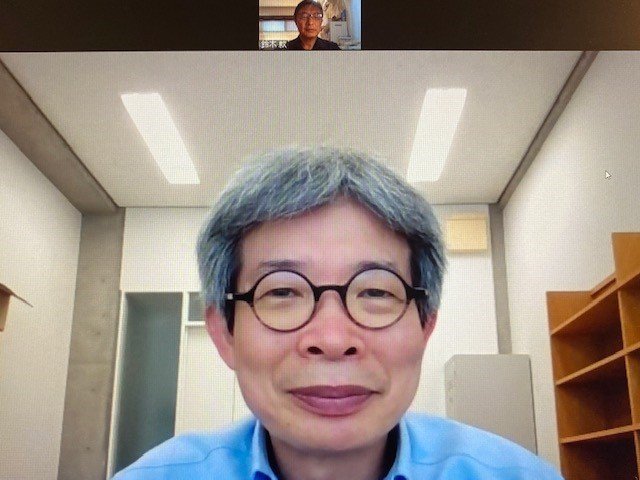
――学長に就任される国際観光芸術専門職大学(仮称)での取り組みについて教えて頂けますか?
平田氏:
まだ認可の申請中ですが、開学すると日本で初めて演劇やダンスが本格的に学べる公立大学という位置づけになります。これは演劇界の悲願でもありましたが、逆に言いますと世界中のほとんどの国は、すでに国立大学に演劇学部があるので、これはある意味恥ずかしい状態でもあったのですね。
もう一つの特徴は観光です。インバウンドが急増して経済的にも注目を集めるようになったのですが、今後はリピーターに来てもらわないといけないと。そのためにスポーツや食文化も含めたコンテンツ、文化観光にシフトしていく必要があって、日本が弱いこの分野で企画や運営をできる人材を作るのが狙いです。
――世界では演劇学部があるのですね。
平田氏:
世界的には美術大学や音楽大学があるのと同じように、演劇の大学があります。また多くの国では高校の選択必修に演劇があります。日本では音楽と美術と書道ですが、海外は音楽と美術と演劇で、当然演劇の先生が必要なので、その意味でも大学にも演劇の学部があるわけです。
――演劇は何歳くらいから学び始めるのですか?
平田氏:
それはいろいろですけど、韓国では4,5年前にすべての高校で科目の選択肢に入りました。台湾やシンガポールでも、そういう高校が多いので、日本はアジアの先進国の中で少し遅れを取ってしまっているかたちです。
小学校でやるかどうかは国ごとに違っていて、演劇という科目があったり、国語の中で学んだり、「表現」という広い科目があったりしますね。
日本でもワークショップをやると、子どもの反応はいろいろですけど、基本的には普通の授業よりは楽しいので。ただ中学でいきなりやると思春期なので照れちゃいますね。
韓流ドラマや韓国映画が日本より評価される理由
――韓国では特に演劇が盛んだと聞いていますが。
平田氏:
韓国はいま映画や演劇などに関連する学部がある大学が95程度あって、人口比でいうと日本の20倍だといわれています。これが韓流ドラマや韓国映画のスターたちやスタッフを支えているということですね。彼らは大学で演劇教育を受けているので古典の教養もありますし、韓国の民族衣装の着付けや殺陣などの基礎を習っています。だから韓流スターは現代劇も時代劇も出来るのですね。

――韓国は今年のアカデミー賞で作品賞を取りましたし、Netflixのドラマ「愛の不時着」は日本でもブームとなっていますね。
平田氏:
韓国の映画やドラマの特徴は、脇役まで演技が上手いんですよ。競争が激しいので、全員のレベルが高いのですね。国としても文化芸術をバックアップしていて、文化予算を対GDP比でみると韓国は日本の約10倍です。数年前フランスを抜いて、文化予算の面だけで見れば世界一の文化大国になっています。
国としてコンテンツ産業を戦略的に輸出しているからですが、例えばシンガポールやクアラルンプールの空港に降りると、韓流スターの出ている化粧品のポスターばっかりです。韓国は化粧品と韓流スターをセットで戦略的に売り出しているということですね。
――日本でも「クールジャパン」など、コンテンツ輸出に力を入れていますが。
平田氏:
韓国の場合は長期戦略でやっています。95の大学が「基礎研究」の場であり、そこから生まれる先端的、前衛的な表現に対しても、ものすごくお金を出しています。それらを背景としながら結果としてK-POPなど大衆的なものも生まれてきています。
韓国は数年前、南米にターゲットを絞り、南米の文化芸術の関係者を韓国に招聘して、伝統芸能から最先端まですべて見せ、南米なら何が受けますかと選んでもらったりしています。
一方日本の海外向けの文化政策は非常に短絡的です。つまり売れるものを作ろうとしてしまっている。また、消費者ファーストではない。日本文化は素晴らしいので発信すれば受けると思っているのですが、そんな甘いものではないですね。
演劇は子どもの情操教育や多様性理解に
――なるほど。演劇教育が国家戦略となっているのですね。演劇を学ぶことによる教育的効果について教えてください。
平田氏:
多くの方は演劇教育というと学芸会のようなイメージが強いと思うのですが、演劇教育は2つに大きく分けられます。演劇そのものの教育と、演劇的手法を使った教育ということですね。演劇そのものの教育は、これまでも情操教育によく、表現力を高めるといわれてきました。もちろん、これも大事ですし、演劇人の私としては、こちらも進めたい。
ただ、最近の主流は、子どもが自分で台本を考えたり、表現の工夫をしたりというグループワークで、「共働性」や多様性の理解によいとされるものです。異なる立場の人を演じるロールプレイによって、他者理解が生まれるということですね。

――演劇は他者理解に繋がると。
平田氏:
きわめて一般的な分類で恐縮ですが、日本人は、会話は出来るが対話は苦手です。日本は「察する」とか「忖度」の能力を競う社会なので、対話の文化は出来ないですね。演劇は作る過程で他者のイメージがはっきりしないといけないので、対話を学べると思っています。
また、小学生の場合には、自己肯定感が高くなることも最近注目されています。東京の私立の小学校ですと、3,4年生くらいから始めるところもありますね。
いま全国で7~80程度の高校で、演劇やダンスを本格的に学べます。そこでは演技指導もしますが、一方で教養科目的に演劇を取り入れている学校も多く、こちらはコミュニケーション教育的なものが主流ですね。

日本の文化芸術支援はなぜ批判されるのか
――コロナによって各国の文化芸術が痛みましたが、支援策は国によって大きなばらつきが出たように見えました。日本の支援についてはどう見ましたか?
平田氏:
実は結果的に額でいうと、日本の文化支援もまあまあ出たのです。ただし、こういった政策はイメージも大事で、例えばドイツは支援の前に「文化芸術は必要不可欠なだけでなく、生命維持装置だ」と言葉にしたわけですね。日本には文化大臣がいないという脆弱さが現れたという点もあります。
もう1つは「アーツカウンシル(※)」といった組織が海外にはあるのですが、これが日本には無い制度的な弱さも出ましたね。
(※文化芸術の事業を支援する第三者機関)
孤立する人が凶暴化した日本の社会
――コロナにおける日本社会のすがたをどう見ていますか?
平田氏:
ステイホームという言葉がありますが、ホームの無い、社会的な関係の希薄な人が日本には一定数いて、この人たちが狂暴化してしまったと思います。ここが盲点で、日本ではこうした人がいるイメージができず、ただ「家にいろ」と非常にネガティブに伝えてしまいました。言葉の使い方が社会状況に影響してしまったのではないかと思います。
自粛警察やSNSの誹謗中傷をマスコミは単純にストレスといいますが、孤独、孤立なんですね。
――人々が孤立する社会が顕在化したと。
平田氏:
もともと中高年の引きこもりや孤独死の問題を日本社会は抱えていて、これをどうするかという課題がありました。私の、もう一つの専門であるアートマネジメントの立場から言うと、企業社会=利益共同体と 地縁血縁社会の中間に、「関心共同体」=趣味趣向などで繋がっているもう一つの共同体が必要だと思います。
最近はサードプレイスともいわれますが、そういう緩衝材がないと孤立者が増える一方です。それが今回コロナで加速したということだと思います。
いまこそ社会教育でも、演劇やダンス、農作業体験やボランティアでもいいのですが、別のつながりを作っていく必要があるということです。もうひとつの社会包括、文化による社会包接がこれから必要になると思います。
コロナで広がる貧富と文化の格差をどう救うか
――最後にコロナとの共生社会、そしてアフターコロナの芸術文化のかたちについて、教えてください。
平田氏:
日本ではこの20年間でCDの売り上げが相当下がりましたが、一方でライブエンタテイメントは4倍、1兆円産業になっています。インターネットの時代だからこそライブの価値が増したのですね。
実はコロナの前からメトロポリタン劇場のライブ配信が有名でしたが、アンケートを取ると9割の人が「本物を観たくなった」と答えています。これまではライブ配信をやると劇場に来なくなるんじゃないかと言われていました。しかしこれまで観なかった層も、本物を観たくなることが統計的に分かっていたのです。
――舞台のライブ配信などアフターコロナは、芸術文化が変わっていきそうですね。
平田氏:
これまでライブ配信はビジネスモデルになっていなかったのですが、ライブ配信の有効性がコロナでますます上がることになり、一方で生の価値も上がるので今後はチケット代が高くなるのではないかと思います。そうすると貧富の差によって文化格差が生まれるので、ますますきめの細かい文化政策が必要になってきます。憲法で保障された「健康で文化的な生活を送る権利」をどうやって国が保証するかがより問われてくるということです。
もう1つは、ネット配信を前提にした新しいアートが生まれてくる可能性もあります。これまでのものをネットで流すのではなく、これを前提にして台本を書くとか、映画の世界でネットフリックスを前提にした映画を作るのと同じような感じですね。
――ありがとうございました。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】





