新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活、国や企業のかたちは大きく変わろうとしている。連載企画「Withコロナで変わる国のかたちと新しい日常」の第18回のテーマは、コロナ禍で追い詰められる中小企業だ。中小企業は日本の全企業数の99%以上、労働者人口の約7割を占めている。今後増加するだろう倒産と失業を防ぐための対策を、自民党で中小企業政策をリードする福田達夫衆議院議員に聞いた。
「人の命を支える」経済の指標も出す時期に

――帝国データバンクによると1月から4月の倒産件数は2800件、今年1年で1万件を超える見通しです。いよいよコロナが実体経済に与える影響が顕在化してきました。
福田氏:
この数カ月間で僕が一番気になるのは、誰も「全体戦略」を描いていないところです。まず、コロナによって生じる経済的ダメージがどのくらいの大きさになるのか。次にどの時期に何をするべきなのか。それによって打ち手の規模と、種類が決まるはずです。
たとえば、3月から5月は「支える」時期ですが、次の6月から8月も「支える」だけで良いのか。実は去年の年末から景気は下降局面でした。たとえコロナを乗り越えたとしても、流れとしては減速基調の経済に戻る、ということを認識すれば、それへの備えも必要となるはずです。

――今後さらに倒産や失業とそれにともなう自殺が増加するおそれがあります。
福田氏:
そろそろ「人の命を守る」感染対策の指標だけでなく、「人の命を支える」経済の指標も出さなければなりません。感染の指標は、感染者数、重症者数と死亡者数ですが、経済の場合、重症者数にあたるのが失業者数、死亡者数にあたるのが経済死の数になります。
――感染と経済の違いをどうお考えですか?
福田氏:
何が違うのかというと、重症者は治るかもしれないし、亡くなった場合には家族や近しい人に心に大きな傷を残します。
しかし、失業や経済死は、近しい人だけでなく社会にとっても大きな痛手となります。この影響を子ども世代が受ければ、この先20年も癒えることのない社会的な痛みが続きます。感染症と、経済。重傷者(失業)と死亡者(経済死)の数が同数だとするならば、経済の影響はより長く、私たちの生活をおびやかす可能性についても考えなくてはいけません。
中小企業経営者に「考える時間」を
――このコロナ禍で中小企業の支援策を作るにあたって、まず考えたことは何ですか?
福田氏:
たとえ売り上げが立たなくても固定費さえ払っていれば、企業は基本的に存続できます。固定費の中で一番大きいのが人件費、2番目が家賃、3番目以降は業種によって異なりますが、光熱費やリース、そして税金。とにかく固定費をいかに肩代わりして、事業と雇用を維持できるかを考えました。

――その一つが持続化給付金ですか?
福田氏:
一番やりたかったのは、中小企業の経営者に「考える時間」を持っていただきたかったのです。未曽有の事態ですし、売り上げが立たず、しかも特効薬とワクチンが出来るまで2年続く可能性もある。その中で、まずは「数ヶ月間はとにかく月末の支払いを心配しなくてもいいんです。その代わりじっくり考えて下さい」というメッセージを伝えたかったのです。
我々が考えたのは、会社もそうですが、会社の向こう側にある生活を守ることです。つまり、雇用を維持してもらい、全国の多くの家庭をとにかく早く助けるために考え出したのが持続化給付金でした。
「何にでも使える」持続化給付金の対象拡大
――しかし持続化給付金は「焼け石に水」とも批判されています。
福田氏:
持続化給付金は、贈与契約であり、国が法人に対して贈与するのは初めてのことです。持続化給付金という「何にでも使えるお金を出しましょう」というのは、大きな発明だと思っています。
額が思っていたより小さくなってしまったというのは正直言ってあります。しかし、たとえば地方の小さなレストランで、持続化給付金を最大200万円受けてもらう。そうすれば2ヶ月、経営を維持できるのではないか。3月と4月はこれで耐えてもらい、それに無利子無担保融資があれば、5月までは何とか体力を温存していただけるのではないか、ということで、パッケージを考えました。

――第二次補正予算案では、対象が広がりましたね。
福田氏:
第二次補正予算案では、今年1月から3月末までに創業した事業者やフリーランスなど個人事業主の方々も申請が可能となりましたので、是非、この給付金をご利用いただき、ひとりでも多くの方が困難を乗り越え、もう一度立ち上がる足腰を作っていただければと強く思っています。
――ただ地方の零細企業ならとりあえずこれで大丈夫かもしれませんが、都市部の中堅企業になるとこれでは厳しいです。
福田氏:
たしかにそうですね。私たちもそういう状況を想定はしていました。ただ家賃の高い場所というのは、地方自治体に力があります。たとえば東京はカナダと同じ財政力持っています。だから、東京は東京の企業を自分の資産としてもう少しフォローしてほしいという思いはあります。というのも、国政は地方も見るし東京も見るので、「平均値」での政策となるものですから。
雇用調整助成金は上限引き上げへ
――雇用調整助成金についてはどうでしょうか?
福田氏:
支援策の中で足並みが揃わなかったのは、雇用調整助成金といえるかもしれません。ふつうの経済危機の場合、海外の需要縮小から始まり、大企業からだんだん街の中にくるというパターンだったのですが、今回はいきなり街中に入り、しかも小規模事業者にいきなり来てしまいました。
――中小零細企業にとって雇用調整助成金は手続きが煩雑で、申請を諦めるところも多いと聞いています。
福田氏:
雇用調整助成金は、労働管理などがある程度出来ている企業向けにつくられています。今回、需要蒸発が直撃した事業者は比較的小規模が多く、必ずしもそのような規約を持たないところも多かった。また、申請をする経験も無い中で、緊急対応として活用されなかったというのが現実です。
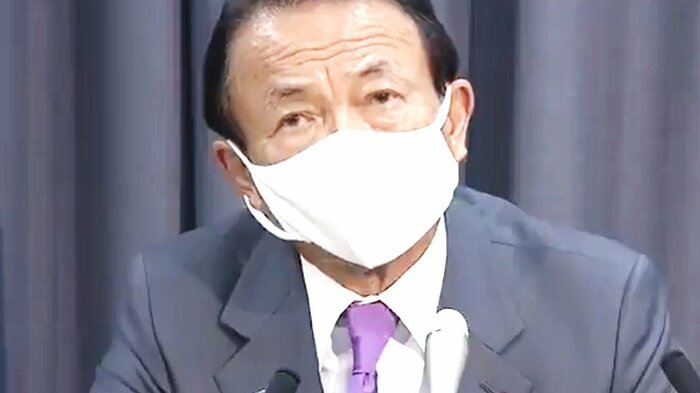
休業手当を受け取れない人への支援金も創設
――そもそもはリーマンショック時の制度でしたね。
福田氏:
そもそもこの制度は、リーマンショックの時に、虚偽申請による支払いを後日だいぶ批判された経緯があり、「羹(あつもの)に懲りて膾を吹く」ではないですが、あまりオープンに制度を作れなかったのですね。我々は最初3月から5月期は企業に雇用を維持してもらうのを目指していましたが、いまは厳しい状況が続いています。
――政府では月の上限額を引き上げますね。
福田氏:
これまでも、雇用調整助成金の申請基準は緩和されています。もともと企業の休業手当は、普段の給料の6割から8割という決まりでした。しかし中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、雇用調整助成金が100%出るようになっています。
ただし、8330円という上限については、1日研修をすれば助成金額の上乗せも行われていますが、さらに抜本的に拡充すべく今般、1万5000円まで特例的に引き上げが決まりました。
また、雇用調整助成金と同じ月額33万円を上限に、勤め先から休業手当を受け取れない人が直接申請して、国が直接給付する新たな制度・新型コロナ対応休業支援金も創設しました。
小規模事業者向け補助金や家賃支援の給付金も
――無利子無担保融資も、持続化給付金、雇用調整助成金と並ぶ柱ですね。
福田氏:
無利子無担保融資では、日本政策金融公庫だけでなく民間金融機関でも当初3年間金利負担が実質的に無利子になります。また、資金繰り支援に加えて企業の財務基盤の強化に向けた出資も並行して進められるよう、資本支援策も手当てしました。
――ほかにも小規模事業者向けの補助金があると聞きました。
福田氏:
持続化給付金と似た名前で、小規模事業者持続化補助金もあります。普段は上限50万円ですが、小規模事業者には100万円給付されます。さらに事業再開支援として50万円上乗せもされます。もちろん持続化給付金と両方給付されます。
こうして組み合わせて頂くと、これまで出来なかったチャレンジも出来ると思います。これは各地域の商工会議所、商工会、よろず支援拠点などにぜひ問い合わせて頂ければと思います。
――家賃についてはいかがですか?例えば国から家主に対して、家賃の支払いを減免するよう要請することは可能ですか?
福田氏:
国交省が3月段階から、家賃を減免してくれた場合には、来年度の固定資産税を減免か、場合によっては免除したり、家賃を減免したことによって赤字が出た場合は、昨年度分の利益の繰り上げも出来るなどの対策をしていました。
その後の議論で、より直接的な支援をということになり、第二次補正予算において最大半年で600万円を助成する家賃支援給付金を新たに創設しました。そもそも持続化給付金は固定費の肩代わりなので、その中に家賃も含まれるはずだったのですが。
アフターコロナで変わる企業経営
――こうした支援策がうまく回り出して、中小企業の持続に繋がることを期待します。
福田氏:
我々は事業者さんに、会社・お店と従業員さんを手放さないでほしいのです。これをいったん手放してしまうと回復の主役がいなくなってしまいますし、社会や家庭に与える影響も大きいのです。経済がいつ回復するか分からないですが、このお金をその時の街の活力源として欲しいと思います。
――コロナがいつ収束するかわかりませんが、アフターコロナに向けて企業経営のかたちも変わりそうですね。
福田氏:
今回の外出自粛で、人と会わないという形がだいぶ進展しましたから、コロナの前と同じというわけではなく、経営の仕方も変わると思います。
また、世界に目を転じれば、世界的な産業再編や産業構造の転換も多分起きると思います。こういう変化の流れの中で、私たちは中小企業・小規模事業者政策をどうするのかも考えなければいけません。

――ありがとうございました。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】





