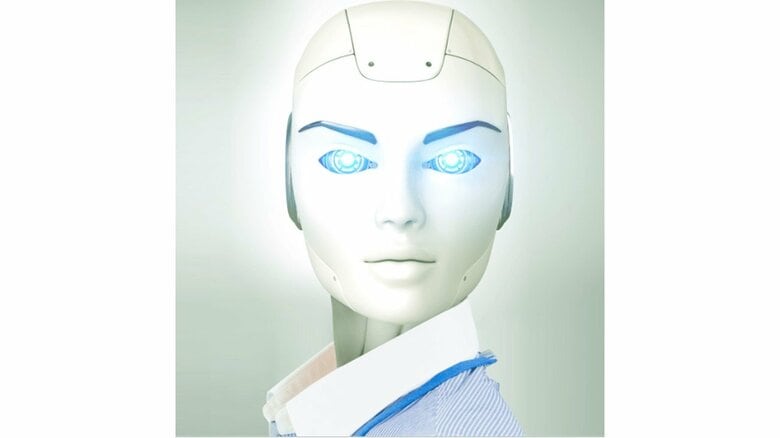新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活、国や企業のかたちは大きく変わろうとしている。これは同時に、これまで放置されてきた東京への一極集中、政治の不透明な意思決定、行政のペーパレス化や学校教育のIT活用の遅れなど、日本社会の様々な課題を浮き彫りにした。
連載企画「Withコロナで変わる国のかたちと新しい日常」の第13回のテーマは、近年導入が進んでいるRPA=ロボティック・プロセス・オートメーション、ロボットによるオフィス業務の自動化だ。RPAが新型コロナウイルス対応で逼迫する医療現場やリモートワークによって無人化したオフィスの救世主となるのか、その未来を取材した。
大企業の4割はRPAを導入済み

「2013年に経営コンサルティング会社として立ち上げたのですが、大量の請求書の送付など業務が煩雑で、これを何とか自動化できないかと考えました。最初はユーザーとしてRPAを導入したのですが、活用しているうちに自分たちのサービスとして提供する価値があるなと思い始め、RPAのサービスを始めたのです」
企業のRPA導入を支援する株式会社副社長の代表取締役、髙室直樹氏はこう語る。
RPAは2016年が「元年」と呼ばれるが、その後急速に普及し昨年の調査会社の調べでは3社に1社がRPAを導入、特に大企業では既に4割近くが導入している。たとえば金融でも三井住友フィナンシャルグループは、3年ほど前からRPAを積極的に導入し、業務改革に取り組んでいる。
導入の背景にあるのは、近年の日本の労働市場の人手不足と働き方改革による残業時間削減だ。各企業では生産効率を上げ、人的資源を成長領域へ振り分けるために、とくにホワイトカラーの事務作業をどうやって減らすのか頭を悩ませていた。こうした中現れたのがRPAだった。
オフィス無人化でリモートワーク推進
「数年前は導入の初期費用に数千万円、月額数百万円の費用がかかりました。しかしいまは初期費用ゼロ円、月十万円前後というものも現れて導入しやすくなり、かつ性能も上がりました。RPAはAIと違い勝手に『判断』をしてくれないので、手順を教えていく作業が発生します。一つ一つの手順を新人のアルバイトに教えていくような感じでしょうか。プログラム言語がわからなくても操作出来るものもあります」(髙室氏)
副社長では顧客企業が100社以上あるが、導入サービスは様々だ。例えばネットで製品の注文を受けると自動的にダウンロードするものから、交通費計算といった手間のかかる社内業務もあると髙室氏は言う。
「例えば営業マンが交通費精算の際、行き先の駅名だけ入力すれば、RPAが交通料金を探し出して入力し、PDFデータにして担当部署に書面付きでメールしてくれます。こうすれば提出忘れも金額の入力ミスも無いですし、ダブルチェックをする必要もありません」
外出自粛要請でリモートワークが推奨される中、その障壁となるのがハンコや紙の文化だ。
RPAはこうしたアナログ作業を代替することはできないが、オフィス無人化や残業削減の支援ツールとしてリモートワークを促進するのは可能だ。

「人がわざわざしなくてもいいことは、どんどんRPAに任せて、人は人でしか出来ない仕事にシフトしていく。いまはコロナのためどの企業も目の前のことで精一杯ですが、中長期的にはRPAによってさらなる業務自動化に向かうと思います」(髙室氏)
逼迫する医療現場をRPAが支援する
コロナへの対応で業務が逼迫している医療現場でも、いまRPA導入の動きが加速している。病院へのRPA導入などを支援するRPAテクノロジーズの代表取締役社長・大角暢之氏はこう語る。
「弊社は、去年9月に大学病院の皆様が設立したメディカルRPA協会と連携しております。コロナの対応で医療現場では事務処理が急増しており、医療事務処理を担当するRPAを提供させて頂いています」
医療事務におけるRPAの活用は、たとえばこうだ。
「コロナとの関係が疑われる肺炎の手書きの問診票があるとします。それをスキャンすると、あとはRPAが手書きの文字を認識して、あっという間に電子化し、補正をかけながら電子カルテに入力することができます。また、医療も同様、会計事務処理もRPAが代行します。請求書の作成では、女性事務員が朝早くから来て1日数百枚をシステムに手打ちしていたものを、RPAがやると数分かからず、またミスもないのです」(大角氏)

日本の「ガラパゴス医療」が障壁に
メディカルRPA協会では、医療事務のRPAを各病院で共通化し、シェアすることを目指している。しかしこの障壁となっているのが、日本特有の「電子カルテ」の存在だと大角社長は言う。
「日本だけがガラパゴスのようになっています。患者の医療情報は、ほとんどの国で患者個人のものです。しかし日本は病院のものという考え方がいまだ多くあり、RPA導入の際も、病院の共通プラットフォームが作りづらく、どうしてもオンプレミス=自社運用のシステムで、電子カルテ中心に事務が組み立てられてしまうのです」
ただ医療機関もコロナ対応で現場が逼迫する中、出来るだけ業務を簡素化したい。
「非競争分野、バックオフィスや会計処理に関わるようなものであれば、皆さんでシェアをしようという考え方が、このwithコロナでご了解頂けるようにはなったかなと思います」(大角氏)
アフターコロナはRPAと共に働く
AIやロボットの導入で、人間の雇用が奪われるという論がある。しかし、大角氏は「いまは誰も自分の雇用が奪われるなんて心配していません。特に人手不足の地方では」と一蹴する。
「私はRPAと言わず、デジタルレイバー=仮想知的労働者と呼んでいます。人間が行う単調な作業は、RPAが行う。但しAIと異なりRPAはイレギュラーな対応ができません。そこは最初から織り込んで、人間が行うことになります。人間とRPAが職場で共存し助け合う。これがRPAを仮想労働者と呼ぶことの本質なのです」
今回日本政府は、時限的にオンライン診療を解禁した。大角氏は言う。
「コロナ禍は大変なことですが、今回オンライン診療が認められたことで、AIを活用した診断を全国の病院で共有出来る時代が来るのではないかと思います。足元では仮想労働者とAIを組み合わせた実証実験も進みつつあります」
アフターコロナの医療現場では、RPAやAIと共存した新しい日常の姿が見られるのだろう。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】