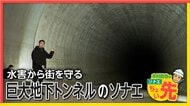4月から毎日、「ニュースちょい先」と題して、木村拓也キャスターが中継をお伝えします。
ニュースワードから連想されるワードをAIが解析し、そのちょっと先から中継するというコーナーです。
東京・群馬・北海道などでは、1日から「カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。
都が出しているものでは、具体的には飲食店などで客が「人格を否定する言動」をしたり、「長時間の居座り、付きまとい行為」などを行った場合、これらが“カスハラに該当します”という、いわゆる定義付け、線引きを決めたというものです。
そんな中、2日は東京・新宿区新大久保にある「皆中稲荷神社」にやってきました。
“皆中”とあるとおり“みなあたる”ということで、絵馬も的を射ていて、“ライブのチケット当選”や“推し活”で特に若い女性がよく来るということです。
この神社とカスハラ防止条例が一体どんな関わりがあるのか「ちょい先AIマップ」で見ていきます。
「カスハラ防止条例」を真ん中に置き、AIで様々なワードを連想していくと、「客」から「神様」につながりました。
“お客さまは神様です”なんてよく言われたり議論されたりしますが、2日は皆中稲荷神社の神主・鶴田裕信さんに話を聞いていきます。
皆中稲荷神社に参拝に来る人は皆さんいい人だといいますが、長くやっていると中には迷惑参拝者、いわゆる“カスハラ”に該当するような人も過去にいたそうです。
どんな人だったかを聞くと、「札所」というお守りをいただくような場所で、お守りを巡って40歳ぐらいの男性が鶴田さんに難癖をつけてきたといいます。
「不良品」と言って「交換」を迫る男性に「神社でお授けするものは一般のお店の商品とは違うため返品や交換はできない」と言うと、「訴えてやるからな」と実際に言われたそうです。
鶴田さんは毅然と対応をしましたが、皆が皆できるかと言われるとそうではないため、「カスハラ防止条例」がやはり必要になってくるのかなと思います。
あくまでこの条例は、いわゆる「努力義務」のようなもので理念条例ですが、「客の責務」もあれば、「従業員の責務」もあって、事業者においても行うべきことが決められました。
例えば、マニュアルを作ったり、相談窓口を作ったり、カスハラに適切な対応をしてくださいという教育や研修をしたり、被害者が1人で抱え込まないようにということが必要になってくるということです。
いずれにしても“お客様は神様”ではなくて、客もしっかりしましょう、従業員もしっかりと対応しましょう、そして事業者もしっかりしていきましょうということが明確になったのかなと思います。