鉄道開業から150年を迎えた2022年。1872年に旅客列車の運行が開始され、日本の交通事情は大きく変わった。煙を吹き上げながら蒸気機関車が走る様子はまさに文明開化の象徴だ。そんな鉄道が今、転換期を迎えている。
止まらぬ人口減少にマイカーの普及、さらには新型コロナウイルスの感染拡大が大きな影響を及ぼしている。そんな中、JR東日本は、初めて、利用者の少ないローカル線の収支を明らかにした。
ローカル線赤字 総額679億円
JR東日本が、今年7月に公表したのは、1日の平均乗客数を示す「輸送密度」が2000人に満たない35路線66区間の収支で、2019年度、20年度ともに、全ての区間で赤字だった。

その後、11月には2021年度の収支も公表されたが、ここでも全ての区間で赤字になっていて、すでに、長い間にわたって赤字が常態化していることが浮き彫りになった。
21年度の赤字総額は679億円に上り、区間別で赤字額が最も大きいのは羽越本線の村上(新潟県)―鶴岡(山形県)間で約50億円。次いで、奥羽本線の東能代(秋田県)―大館(秋田県)間の約31億円だった。いずれの年度でも、この2区間が、赤字額1位・2位を占めた。
100円稼ぐのに「2万円」かかる
また、100円を稼ぐために、どれだけの費用が必要かを表す数値も公表された。21年度、この費用が最高だったのは、陸羽東線の鳴子温泉(宮城県)―最上(山形県)の間だ。この区間は100円を稼ぐために「2万31円」かかっているという。

運行すればするほど、赤字になる計算だ。1日当たりの平均通過人員はわずか44人にとどまっている。関係者の間では、極端に利用者数の少ない路線の在り方について、問題視する声も出ている。しかし、JR東日本は、赤字だからと言って、すぐに廃線にする訳ではないと強調している。
ただ、収支の公表を決めた理由として、「(収支が)厳しいという言葉だけでなく、どのくらい厳しいのか実態を理解していただくため」とした上で、「厳しい線区は、一層厳しさを増すことが見込まれる。何か手を打たなければならない」と危機感を露にした。
鉄道廃止・バス転換も議論
一方、ローカル線の赤字問題については、国も重い腰をあげ、国土交通省が検討会を開き提言をまとめた。それによると、「輸送密度」が1000人未満の区間などを対象に、鉄道を廃止し、路線バスに切り替えることなどを検討するよう求めている。
運営コストは、鉄道よりもバスの方が低いとされる。これから、国が中心になり、鉄道事業者や沿線自治体が参加する新たな協議会の設置を進める方針。すでに、当事者同士では議論が進められている地域もある。国が関与する協議会は、23年夏以降に、本格化する見通しだ。
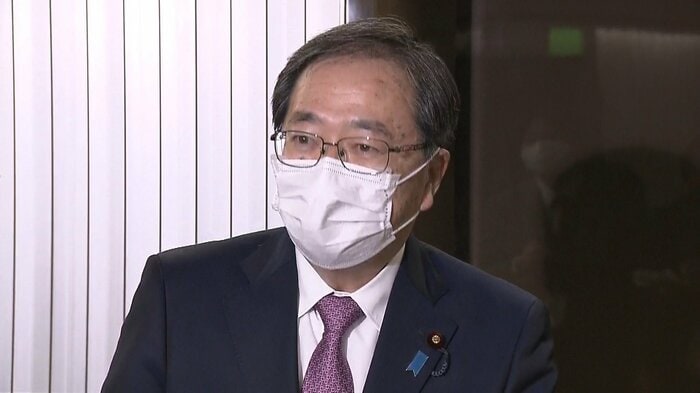
さらに、23年度からは、赤字が続くローカル線の再構築を含む地域公共交通の見直しについて、「公共事業」と位置付け、自治体に財政支援を行う。道路や公園などの整備を補助する「社会資本整備総合交付金」の基幹事業として新たに「地域公共交通再構築事業」を創設。駅や線路などの鉄道施設や、停留所や車庫などのバス施設の整備費などを支援する。
国交省は23年度の交付金から、こうした事業に50億円程度をあてる考えで、斉藤国土交通大臣は、鈴木財務大臣との23年度予算編成の閣僚折衝後、「地域公共交通はまさに今、危機的状況だ、民間活力を最大限引き出しつつ官民共創による地域公共交通ネットワークの再構築に取り組む」と述べ、「23年は大きく地域公共交通の改革に向けて踏み出す年にしたい」との考えを示した。
”都市部”の黒字で穴埋め困難に
ところで、この“ローカル線赤字問題”は、都市部の住民にとっても、決して、人ごとではない。実際、赤字路線を運行する費用は、乗客数が多い都市部の在来線や新幹線の利益などで、穴埋めされているのだ。
しかし、そうやって支えてきた赤字路線だが、新型コロナの影響で、その構図は崩れた。出張での新幹線利用は減り、テレワークの定着により、通勤で電車を利用する人も減少。止まらぬ少子化の影響で、通学に電車を使う学生も減る一方だ。

今後も、乗客数は、コロナ禍前には、完全に戻らないと見込まれている。そんな先行きに、ローカル線の赤字が、重くのしかかることになる。鉄道があるところには人々の生活がある。存続か廃止か、結論を出すのは簡単ではないだろう。
ただ、これまでと同じ”やり方”が通用しないのは間違いない。多くの人が納得のいく形で、赤字ローカル線の行く末を決めることができるのか。国や鉄道事業者、沿線自治体の手腕が問われている。
(フジテレビ社会部・国交省担当 井上文那)



