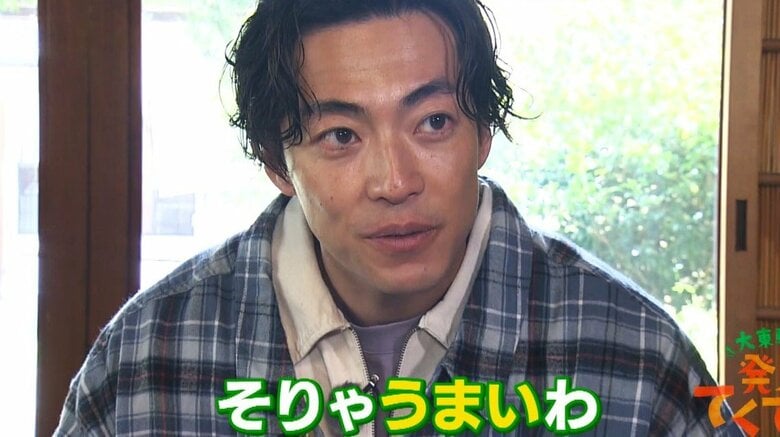俳優の大東駿介さんが、関西の街を歩きながら魅力を学ぶ「発見!てくてく学」。
今回訪れた「ならまち」は、江戸時代から明治時代にかけての町家を利用したカフェや雑貨屋などが集まる、奈良観光の人気スポットです。
ならまちにある「中谷堂」は「高速餅つき」で有名なお店です。ただのパフォーマンスではなく、蒸したてのもち米を熱いうちに仕上げるための技で、高速でつくことで、やわらかくコシのある「よもぎ餅(1個200円)」を作ることができるのだそうです。
「よもぎ餅」のほかにも、奈良に来たなら食べておきたいグルメの知られざる秘密を学びます。
■奈良の新名物 古民家で味わう透明ぷるぷる「水晶餅」
大東さんが訪れた「奈良水晶」は、2023年にオープンした古民家カフェ。いまSNSで話題のフォトジェニックなスイーツ「水晶餅」を提供しています。ぷるぷるで透明なお餅の中に、食べられるお花が入った、美しくおいしい一品です。
店主の菅佳奈さんは、「うまいもんなし」と言われている奈良を盛り上げるために試行錯誤を繰り返し、おいしくて映えるスイーツを開発したのだそうです。
■日本のカレーのルーツは奈良?
以前、大阪の船場で日本初とされる「カレー粉」が誕生したことを学びましたが、日本のカレーのルーツは実は奈良かもしれないといいます。
創建710年、1300年以上の歴史を誇る「興福寺」の執事長・辻明俊さんは、カレーをこよなく愛するお坊さんです。
辻さんによると、こしょう、クローブ、シナモンなどの香辛料が、奈良時代に唐や東南アジア、インドから薬として入ってきたそうです。平城京が都だった756年、正倉院の宝物庫にはスパイスが納められていました。
さらに中世の僧侶が書いた「多門院日記」では、「皮アカキ袋」を食べたら「辛さで内臓が消し飛んだ」という記述があります。これが日本で最初の唐辛子の記述ともいわれています。
■「ならまち」はカレー屋激戦区
そしていま、ならまちは多くのカレー屋がひしめく激戦区になっています。
話題のお店の一つが「菩薩(ぼさつ)カリー」です。「奈良をカレーの総本山にする」をコンセプトに5年前オープンしたお店で、看板メニューはネパールの国民食「ダルバート」です。「ダル」は豆スープ、「バート」はご飯のことで、2種類のカレーと副菜がたっぷり盛り付けられています。
【大東駿介さん】「めちゃくちゃうまいわ」
【辻明俊さん】「だしや酸味が追いかけてくる」
1300年以上の時を超えて受け継がれてきた、日本のスパイス文化に触れた大東さんでした。
【大東駿介さん】「奈良はスパイスと縁がある。辻さんに歴史を教わって、ともにカレーを味わいました」
▼大東さんの“発見”の全ては、動画でじっくりお楽しみください。
https://youtu.be/zieTfFIkIXU
(関西テレビ「newsランナー 大東駿介の発見!てくてく学」 2025年5月1日木曜日放送)