東京五輪で悲願の金メダルを獲得し、この夏、フェンシング界に新たな歴史を刻んだ男子エペ団体。
キャプテンの見延和靖(34)、エースとして奮闘した山田優(27)、途中出場で流れを変えた宇山賢(29)、そしてアンカーとして勝負を決定づけた加納虹輝(23)の4人は、記者会見である人への「感謝の言葉」を口にしていた。
「世界一のグローブをつけたからには世界一にならないといけなかった」(見延)、「細川さんにはありがとうという気持ちで一杯です」(山田)と、世界に大きな衝撃を与えた彼らが語ったのは、アスリートと共に夢を掴んだ75歳と72歳、夫婦であり職人でもある2人に向けた言葉だった。
日本唯一のフェンシンググローブ職人

東京から約700キロ離れた香川県・東かがわ市。その自慢は手袋生産で、国内シェア90%を誇る。

その街で育ち、手袋工場「スケルマ」を営むのが細川勝弘さん(75)、そして妻のかずゑさん(72)。日本国内で唯一フェンシンググローブを手がける職人だ。

オリンピックで日本初のメダルを獲得した太田雄貴さんを始め、もちろん、男子エペ団体メンバーも愛用。
宇山は「中学2年生の頃から使っています」、見延は「細川さんはTHE職人、市販のグローブとはまるで違いますね」と信頼を寄せる。

およそ30枚もの生地を複雑に縫い合わせてできる、細川夫妻のグローブ。その全ての工程を2人だけで、しかも手作りで仕立てている。
「一日に4枚程度。歳がいったら大変なんですよ。選手の顔を思い浮かべながら作っとります」と、一つ一つ丹精込めて仕上げていく。
「明日、食べる米も無かった」道のり

今や国内だけでなく海外からも発注がくるなど、忙しい毎日を送る細川夫妻だが、夫婦2人での経営は簡単ではなかった。
33年前、長年勤めた会社を辞め、自らの手袋を作るという夢を追いかけた勝弘さん。

「冬用の防寒用いうたら、残りの半分は仕事がありませんもんね。ほんまの自転車操業ですわね。その時期は、明日食べる米も無かったもんね」
その言葉の通り、日々を生き抜くことで精一杯だった2人。
そんな中、16年前、選手だった次女の夫の依頼をきっかけにフェンシンググローブ製作に挑戦する。
「家内に無理を言って1万円もらって会場の京都へ行ったんです。会場に行ったら『ワー!』といってものすごく盛り上がっていたんですわ。走りこんで行ったら、私のところのグローブをつけた選手が優勝してたんです」
ここから本格的にフェンシンググローブの生産を始めた細川夫妻。地元の学校や試合会場に足を運んではアドバイスを求める日々。2時間睡眠が続く時もあったという。
たどりついた“素手感覚”
夫妻がたどり着いた一つの答えは、“素手感覚”だった。

「海外の製品は手のひらが真っ平らなんですよ。ウチの“スケルマ”グローブは半立体になってるんです。アイロンを使って型をつけるんです」

緻密な縫製と特殊なアイロンを使うことで、指先が手をはめる前からコの字型に曲がっているのが、スケルマのグローブの特徴。海外製は指を曲げるとシワができ、剣を握る時に違和感が残るが、スケルマのものは、より素手感覚で剣をさばけるという。
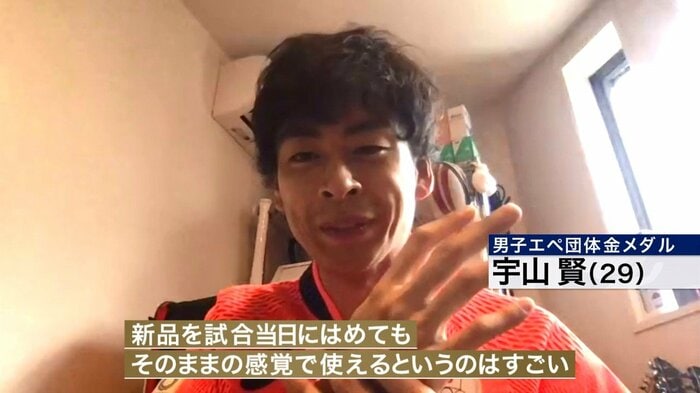
見延は「ほんとはめた時のストレスってのが一切ないですし、だからこそ指先に神経が行きますし、細かい動きができる」と評価する。宇山も「新品を試合当日にはめても、そのままの感覚で使えるというのはすごいなと思います」と絶賛だ。
「選手と同じ舞台に立てるのが一番の喜び」
東京オリンピックは細川夫妻にとっても集大成だった。

「1つの物を作るのに3回から4回くらい修正していくんですわ。1日でようやく1枚の手袋ができる」
選手たちが最高の結果を残せるよう、微調整を繰り返し、選手の元へグローブを送り終えたのは選手村に入る2日前だった。
迎えた大一番。選手たちの手には細川夫妻が魂を込めたグローブがはめられていた。
「自分の手袋が出て行って、選手と同じ舞台に立てるのが一番の喜びでしたね」
そして、細川夫妻の思いも背負った選手たちは、日本中を沸かせることになった。
その姿を目にした勝弘さんは、「涙が出てテレビなんか見れませんでしたね…縫製業を辞めんで良かったですわ…」と涙を流した。

「『もうお母さん、ワシはいつ死んでも構わん』と。『何も思い残すことはない』と、いつも言いよるもんな。もう今が本当に一番幸せな時期ですわね」
パリへと続く職人夫婦の物語
そんな2人に宇山と見延からビデオメッセージが、届けられた。

「細川さん!ビールでも交えて報告したいと思いますので、そのときまで待っててくださいね!!」(宇山)
「3年後のパリも目指してますし、改良点も見つかってるので、また相談させてください。香川にもお邪魔します。お元気で!」(見延)

妻・かずゑさんは「改良点が見つかった言われた(笑)、また作るの大変やね」と、夫のやる気を引き出すように語りかけていた。
日本フェンシングと、それを支える職人夫婦の物語は、3年後のパリへと続いていく。




