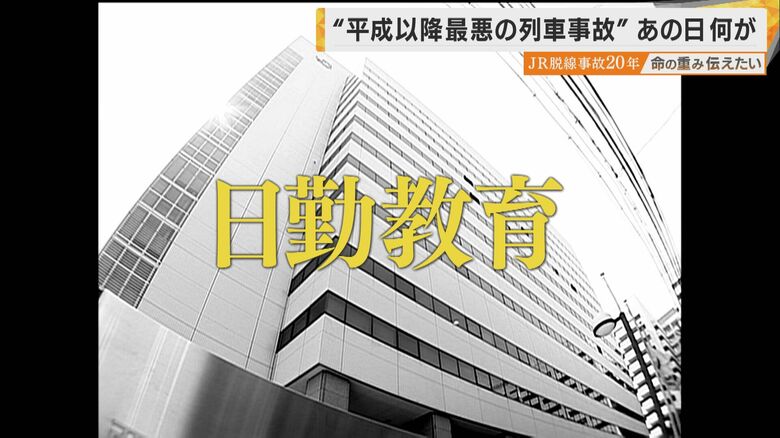乗客106人が犠牲となった事故の背景には、JR西日本の組織としての体質があったと指摘されています。
あのとき、一体何があったのか。
そして、20年がたち、JRは変われたのか。今だからこそ、考えます。
■事故の日とその背景
2005年4月25日、JR福知山線で発生した列車脱線事故は、乗客106人と運転士の命を奪い、平成以降最悪の鉄道事故とされている。
その日、当時23歳の運転士は、伊丹駅で72メートルのオーバーランを起こし、10カ月前にも同様のミスをしていた。
運転士は「またあの厳しい教育を受けなければいけない」と、過去の経験が彼に影を落としていた。
■日勤教育の実態
事故を引き起こした背景には、JR西日本の企業文化が影響していたとされる。
特に、運転士に対する管理体制は、「パワハラ的」とも言われるもので、運転士のミスに対して過酷な“日勤教育”が行われていた。
この教育はペナルティとも取れる厳しい内容で、運転士を精神的に追い込むものだった。
JR西日本の広島の運転士が、69日間「日勤教育」を受け、就業規則の丸暗記を命じられたときの音声が残っている。
【広島の運転士】「頭がパンパンになっているような状態で、もうあっさりした方がいいかな。死の方が…。何でここまでさせられるんだろうと思って」
■事故当日の運転士の心理
事故当日、運転士は伊丹駅でのミスで再び日勤教育を受けることを恐れ、車内電話で過剰申告を求めていた。
しかし、列車は事故現場のカーブに差しかかり、ブレーキをかけるタイミングを19秒も遅らせたため、進入速度は制限速度の時速70キロを大幅に超える116キロに達してしまった。
その結果、100人以上の命を奪う大惨事となった。
■事故後の変化と課題
この事故を受け、JR西日本は安全最優先を掲げ、乗務員が故意でないミスをしても、処分の対象としない制度を導入した。
また、事故後に開始された“安全ミーティング”は今も続いている。
しかし、20年間の間に再び事故が発生するたびに、JR西日本はその教訓を本当に生かしているのかと問われ続けた。
■安全への取り組みの重要性
関西大学の安部誠治名誉教授は、「仕掛けと仕組みはできたが、それを担うのは人であり、これが難しい」と指摘する。
社員の7割がJR福知山線事故後に入社したという現状の中で、事故の教訓をしっかりと理解し、安全の大切さを教育していくことが求められている。
日々の努力を続け、過去の過ちを繰り返さないために、JR西日本の取り組みは続いている。
安全への取り組みは終わりなきものであり、企業文化の改善と人材教育の徹底が求められている。
(関西テレビ「newsランナー」2025年4月25日放送)