フジテレビの一時代を築いた須田哲夫アナウンサー(71)。小学校(1990年代初頭)から帰宅してテレビをつければ、ブラウン管の中に午後のワイドショーの司会をつとめる須田アナウンサーがいる姿は、私にとって日常そのものだった。
その彼が週刊誌に「認知症母 介護の日々」と報じられたのは2016年9月。その翌年には「介護難民危機」とも書かれた。
かつて、優しくもキビキビとした指導をしてくれた彼からは、高齢の母親を抱え困り果てる姿が想像できず、ずっと気にかかっていた。
それから数年。高齢者介護の実態を記事として書かせてもらえないかと、もはや何年振りかわからない電話を彼にかけたところ、全く想像をしていなかった意外な事実を知ることになった。
週刊誌報道はまったく不本意
週刊誌に載った「母親の車いすを懸命に押す須田アナ」の写真は、すれ違いざまに車の中から隠し撮りされたものだった。
その後の直撃取材も「介護難民」という「ワードありき」の取材だったのではないか、と須田さんは疑問を感じていた。
その理由に至る経緯を教えてくれた。
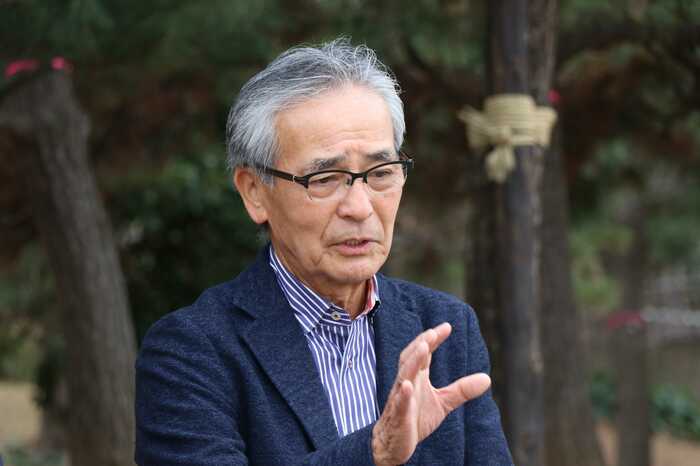
両親は東京・23区内の2階建て住宅の実家で弟家族と暮らしていたのだが、いまから7年ほど前、ガスコンロをつけっぱなしにするなど軽い認知症の症状が母親に出始めた。その後、父親の心臓の持病が悪化し入退院を繰り返すようになるなかで、今度は母親が自宅で転倒し脚の付け根を骨折、自力で歩くことが難しくなっていった。
母親はその後、夜中に自力でトイレにいこうとして、転倒。大きな音におどろき、2階で暮らしていた弟夫婦は飛び起きて助けに行った。そのようなことが何度かあるなかで、弟夫婦と娘は心配で安眠できなくなっていった。
自宅の各所に手すりをつけるなどバリアフリー化をすすめ、ガスコンロも電気式にするなど、弟家族はどうにかして一緒に暮らそうとしていたのだが、須田さんは限界が近づいてきていると感じた。弟と相談したところ、施設に預けることがすぐ決まった。
彼は、一緒に暮らしている弟からは切り出しにくいだろうと思い、自ら両親を説得した。その日、母親は「イヤだ」と拒否したものの、一日かけて話し合い、施設に入ることに同意した。
ケアマネージャーに相談し、2015年12月に見つかったのが夫婦同室で過ごせる「介護老人保健施設」だった。施設はリハビリを重視し、3か月での退所を目途とするところだったが、杓子定規に追い出すようなことはなく、施設側ときちんと話し合いができていた。
2人仲良く暮らす中、翌春に父親が亡くなり、その後、母親がひとりで暮らすようになった。
週刊誌報道はその年の秋だった。報道では“行く当てがない老婆を介護する須田アナ”という流れになっていた。彼は、自身もこれまで数えきれないほどのインタビューをしてきた身だからこそ、不意の直撃とはいえきちんと応じなければと思い、広報から「話しすぎです」と怒られるほど真摯に取材に答えた。しかし、彼が語った“事実”とは少し異なる報道になった。

私が記事から感じた「介護難民化への危惧感を持つ須田さん自らが発した情報」という印象は、彼の本意とは裏腹のものだった。
ただ、もっとも彼を悲しませたのは、目立つことを極端に嫌っていた母親が、自分に知名度があるがゆえに隠し撮りされ、週刊誌に掲載されたことだった。
以後、須田さんは母親に関する取材は一切受けないと決めた。
経緯をなにも知らない私が電話をかけてから二か月半後。
彼は「自分でもどうしていいか答えが見つかっていないから、最初、森下の取材は受けられないとおもった」と、こうした経緯からいまにいたる、すべての思いを話しはじめてくれた。
「ここはイヤなのよね」リビングルームの机に突っ伏す母親
母親は2017年6月、区営の特別養護老人ホームに入ることができた。施設が新設されたとき、その区が地元だったのですぐに入ることができたのだ。
母親の定住先がみつかったことで安心した半面、その後、須田さんは少しずつ悩みを抱いていくことになる。
母親はホームで暮らし始めたとき「ここはイヤなのよね」といった。実家をこよなく愛していたからこそ感じた、慣れぬ居心地の悪さから発せられた思いなのでは、と当時の須田さんは考えていた。

入所から1年がたったころ「不安があったらいって」とたずねた須田さんに「(ここで)いい」と母親は答えた。彼は、その言葉は、あきらめからきたものなのか、気を遣っていったものなのかはわからない、と話していた。ただ私には、彼はきっと母親はそのどちらかの思いから言ったのではないか、と推測しているように感じられた。だからこそ彼は、これでよかったのか、と考えはじめたのだ、と。
スタッフはいつも笑顔で、とてもよくしてくれる。母親も特に不満を言うこともない。毎日おだやかだという。ホームは須田さんの自宅から自転車で10分。平日のほぼ毎日、母親の大好きなクリームパンなどをもってたずねる須田さんに対して、ニコニコしながら「おいしいね」と、ペロッと食べてくれる。そして、母親から「ちょくちょく来てね」と言われながらホームを去る。

「てつお」と呼ばれることもあれば「おとうさん」といわれることもあるから、時に、母親はすでに亡くなった夫と思い込んでいることもあるのだけれど。
ただ、ホームをたずねたとき、須田さんの目に飛び込んでくるのは、なにをするでもなく、だれと話すでもなく、ただ、リビングのおおきなテーブルにひとり突っ伏す母親の姿なのだ。
自宅という自覚がなくなっていた
須田さんと同じ頻度でホームに通う、彼の弟も「母親はここで幸せなのか」という疑問にも似た悩みを少なからず抱えていたのかもしれない。いや、むしろ、長らく一緒に「自宅」で暮らしていたからこそ、胸につかえるものがあったのだろう。
今年1月、親戚・家族ら10数人で母親を囲んで外食をしたあと、弟は須田さんには言わず、母親を車で自宅に連れて帰ってみた。
「自宅という自覚がなくなっている」
弟は反応のない母親をみて感じた。その話を、その後しばらくたってから須田さんは聞いた。
大好きだった「自宅」を認識できない母親。好きな「自宅」ではなくホームで暮らしていることでストレスを抱えてしまっているのではないかという心配。
それは時を経て“杞憂”にかわっていたのだった。
では、逆に、どうしたらいいのだ。

「何かをさせてください」
「非日常をつくることがいいのでは」と介護担当の人にアドバイスされた須田さんは、ホームのスタッフに「母に何かをさせてください」と訴える一方で、はじめの一年は、車いすを押して頻繁に散歩やホームの屋上に連れ出した。何日も、何日も、一緒に歌をうたった。
母親は月に1、2回あるバイキング形式の食事や、地域の保育園児が来るイベントにも楽しそうに参加していた。
ただ、おそらく、それらは一時の解決にすぎず、根本的な物事の解決にはなっていないのだろう。
「これがベストだとはおもっていない。どうすればいいのか、いま探っている」と須田さんは柔和ないつもの顔とは異なる険しい顔で、何度も語った。

ホームのおかげで、お互い安心して生きていける。
しかし、自分を生み育ててくれた母親が、いつ最期を迎えてもおかしくない歳になったいま、この状況で日々、心から幸せに暮らしているのか、という疑問や不安を、ホームのリビングの机に突っ伏す母親の背中から感じとったのだろう。
ただ、ほかに現実的な選択肢がないから答えがみつからない。
「お荷物になっていると自分が感じたら嫌。人間として生きていく尊厳を感じていたい」と、自らも高齢者になることで感じるようになった須田さんは、例えば、ひとりひとりのこれまでの長い人生のバックグラウンドに合った生活を、専門的にアドバイス・提供できる環境があれば、と願っている。
そう願いながら、きょうもホームに自転車で通い、母親の手を握る。
すると、母親はこういって笑顔をみせる。
「あなたの手、やわらかいのね」
そして、その日のうちに、母親は須田さんがきたことを忘れていく。
高齢者の8割が病院で亡くなる現状
厚生労働省の調査によると、高齢者のおよそ6割が自宅で最期を迎えることを希望している一方で、実際は8割が病院で亡くなっている。
この差は、在宅医療を専門とするクリニックの増加などにより徐々に埋まりつつあるものの、福祉がすすむスウェーデンやオランダでは、病院で亡くなる割合は4割前後。のこりのほとんどは、ナーシングケア付き住宅か自宅である。
特にスウェーデンでは、日本の市町村にあたる「コミューン」とよばれる各自治体が高齢者福祉に責任をもち、専属の介護士が一日に何度か住まいを訪ねることで、独り身でも認知症でも9割の高齢者が自宅で過ごすことを可能とする、在宅介護体制が整っている。
日本は医療技術の進歩などにより、世界一高齢化率が高い。これからの時代は、たとえば「安心」のほかに、介護をする側もされる側も満ち足りた日々を過ごすことのできるような、多様な介護の選択肢が求められているのではないだろうか。

(執筆:フジテレビ プライムオンラインデスク 森下知哉)

