長期にわたる休校がもたらす負の影響
5月18日(月)に自民党本部で第3回の「秋季入学制度検討ワーキングチーム役員会」のが行われた。これは、学校の入学や始業を9月にする「9月入学」を検討するために立ち上がったワーキングチームであるが、座長の柴山昌彦前文科大臣のみならず、複数の元文科大臣経験者が参加しており、自民党が「本気」で 9月入学案を検討していることが窺われるものとなっている。同日、筆者は、早稲田大学の田中愛治総長とともに、有識者として意見を述べる機会を得た。

ここでは18日に報告した内容をもとに、科学的根拠に基づいて、9月入学の是非について論じたい。まず、長期にわたる休校がもたらす負の影響が大きい可能性がある点について言及しておきたい。過去に生じた臨時休校がもたらす影響について分析した論文は複数、発表されている。過去の研究では、天候・教員のストライキ・狙撃事件などによって余儀なくされた「臨時休校」が子供の学力や学歴、将来の賃金などに与えた影響を推定しており、こうした研究の結果は一貫している。「臨時休校」の悪影響は決して小さくないということである。

例えば、1990 年にベルギーで生じた2か月間の教員のストライキによって生じた臨時休校を経験した子らは、高校までの留年率が高まり、大学での成績も低下したことが報告されている[*1]。これ以外にアルゼンチンの小学校で発生した 88 日にも及ぶストライキは、学歴への影響のみならず、子供たちが30-40歳になった時の賃金を、男子で 3.2%、女子で 1.9%も低下させたと報告している [*2]。つまり、臨時休校がもたらす学力や学歴、そして逸失生涯所得への影響は小さくない。なお、ストライキの対象となった小学生全体でみれば、年間の逸失生涯所得による損失は 23億4000ドルにも上り、アルゼンチンの全小学校教員の賃金を62.4%引き上げるのと等しい。つまり、臨時休校というのは経済的な損失が大きいので、とかく慎重に判断すべきであると言える。
「臨時休校」から生じる学力格差
そして臨時休校の影響を受けやすいのは、より低学年の子どもである。アメリカのメリーランド州で、降雪等による天候要因が原因で生じた臨時休校は、低学年のほうが高学年よりも悪影響が大きかったことを明らかにしている[*3]。また過去の研究は、特に理数系科目への負の影響が大きいと指摘する。各授業の学習内容が独立している教科と比較すると、過去からの積み上げが重要な算数や数学では、臨時休校中の特定の内容がカバーされなくなることがその後も長期的に影響するというわけだ[*4]。
そこで、学校現場では、遠隔での教育活動を行うことで、世代全体の学力低下を防ぐ試みが行われている。しかし、社会学の研究には、生徒が学校に通わない夏休み期間中に学力格差が拡大することを明らかにした研究は多く[*5]、特に学齢の小さい子供は、遠隔で自律的に学習を行うのは難しい。ここで期待されるのが、オンラインで双方向の遠隔指導を行ったり、e ラーニングなどのデジタル教材を用いることである。しかし、ハード・ソフト両面で公立学校のデジタル化は遅れており、遠隔教育を行う環境が十分に整ったとは言えない。

文部科学省が 4月16日時点で臨時休校すると答えた 1,213の自治体に対し行った調査では、教員と児童・生徒が双方向でコミュニケーションをする遠隔指導を実施している自治体は 4月16日時点ではわずか 5%にとどまっている[*6]。しかも、オンラインの遠隔教育は「魔法の杖」ではない。その効果を実証した研究の見解はいまだに分かれている上[*7]、格差を拡大するとの指摘もある。例えば、スイスの総合大学の大学生を対象にした研究では、学期中、週単位でプラットフォームへのアクセスを無作為化し、同じ学生がオンラインで授業を受けられる週と受けられない週があるように設定した結果、もともと成績の良かった生徒は成績が上昇し、悪かった生徒は低下したことが示されている[*8]。
このように過去の研究を概観してみると、コロナウィルスによって生じた3か月にわたる臨時休校は、コホート全体の平均的な学力を低下させ、コホート内の学力格差が拡大させた可能性が高い。こうした認識は学校現場や家庭にもあり、オンラインの遠隔教育に取り残された児童・生徒の遅れを取り戻し、入試までのリードタイムが稼げるという点で、「9月入学」を魅力的に感じる人も少なくなかったのではないか。
「9月入学」は学力低下と格差拡大の問題解決になるのか

しかし、学力の低下や学力格差の拡大という問題を解決するために「9月入学」という手段が妥当かどうか、ということを検討する必要がある。そして、今回にわかに議論されている「9月入学」が、これまでに議論されてきた「9月入学」と決定的に違っていることは指摘しておく必要がある。従前の「9月入学」は子供たちを5歳の秋に入学させる(=入学を半年早める)ことを念頭においているのに対し、今回にわかに議論されている「9月入学」は子供たちを6歳秋に入学させる(=入学を半年遅らせる)ものだということだ。欧米の多くの国々の就学開始年齢よりも1歳遅れの就学開始年齢となることを考えれば、「わが国の教育システムを国際標準に合わせる」ということにはまったくあたらない。

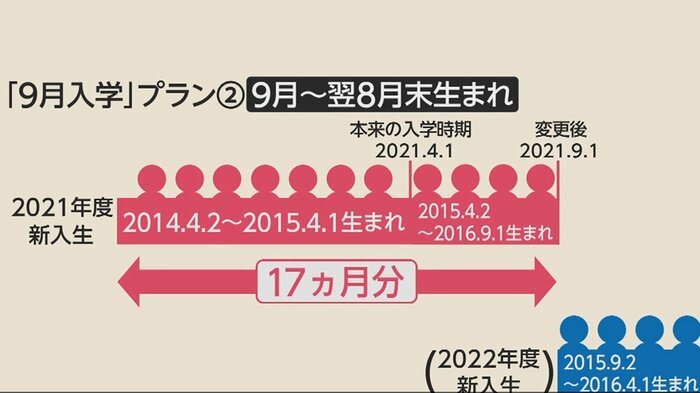
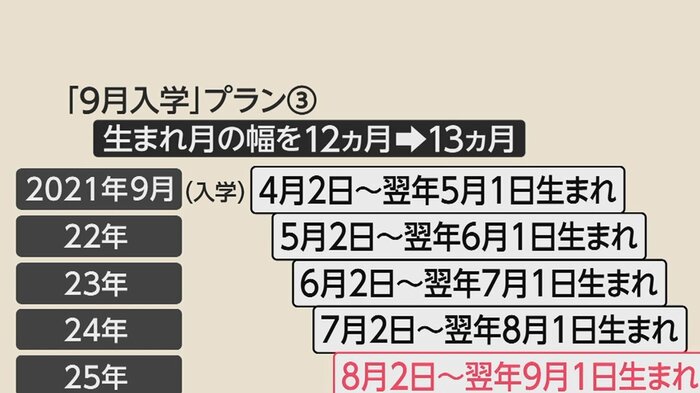
では、まず学力の低下や学力格差への対応として、9月入学が妥当かどうかという点を考えてみよう。アメリカの州ごとの授業日数や時間数の差に着目した研究では、学校での授業日数や時間数の増加は学力にプラスの影響を与えることを示されている[*9]。また、ドイツでは、カリキュラムや全体の学習内容を変更しないまま、1年間の授業日数を37週から24週へ短縮した経験があるが、この制度変更を分析した研究によれば、授業日数の短縮は留年率を高め、高校進学率を低下させたという[*10]。すなわち、カリキュラムや全体の授業内容を変更しないのであれば、失われた3か月分の授業日数や授業時間の確保が必要だということになる。しかし、その授業日数や授業時間の確保は、9月入学でしか実現できないものではなく、夏休みを短縮したり、土曜日に補習をするということでも補うことができるはずだ。

しかし、夏休み短縮のためには、忘れてはならないことがある。アメリカで行われた研究によれば、学期中の気温が 1℉上昇すると1年間の学習量を1%失うという[*11]。この研究では、比較的寒冷な地域では、エアコン設置が普及していないため、かえって夏場の学習効果の低下が顕著になっていることも示されており、寒冷な地域であればエアコン設置の必要がないと考えることは危険である。しかし、令和元年時点の日本の公立小・中学校の冷房設置率は78.4%にとどまっている[*12]。夏休み中に授業を行うのであれば、早急にエアコン設置をすすめることが肝要だ。
入学年齢を遅らせるデメリット
次に、入学年齢を遅らせることにデメリットはないのだろうか。この点についてノルウェーのデータを 用いて行われた研究は参考になる[*13]。この研究は、就学開始年齢が高くなると、IQや学歴には影響はないが、30歳ごろまでの賃金が低くなることを示している。逸失生涯所得の合計は 2007年の物価で 10,000 ドル(107 万円)、ノルウェーの平均年収のおよそ 1/5 程度に達する。24歳時でー10%、30歳時点でー1%と悪影響は年齢とともに小さくなっているが、若い時の逸失所得が大きいと、結婚や出産を遅らせる原因にもなり、少子高齢化や晩婚化に拍車をかける恐れもある。
一方、この研究では、男子の18歳時点のメンタルヘルスの問題は改善したり、女子の10代での妊娠を減少させることが示されているが、筆者としては生涯逸失所得への悪影響は無視できないと考える。そもそも臨時休校によって生じた損失を取り戻す目的で行われるはずの 9月入学で、逸失生涯所得が更に大きくなったというのでは元も子もないからだ。
以上のようなことを考えると、コロナウィルスによる臨時休校の長期化によって生じた問題を、現在議論されているような半年遅れの「9月入学」案で解決しようとすることはリスクが高く、それよりは夏休み短縮や土曜日の補修など、よりリスクとコストの低い方法を積極的に検討すべきではないか。また、就学期に長期の臨時休校を経験した世代が、長期にわたってその悪影響に苦しめられることのないよう、なるべく早期に学校を再開させる道筋を示し、今後も彼ら彼女らの教育に継続的な公的支援をしていくことの方が王道ではないかと思えるし、今まだ生まれてもいないコロナウィルスの影響をまったく受けない世代までもがこの制度改変の対象になることも忘れてはならないだろう。
「9月入学」を実施すべきか否か
ここからは、従来から検討されていた(半年早める)「9月入学」を実施すべきかどうかということについても検討してみよう。
ここでは、政策の「ベネフィット」と「コスト」に分けて議論することが有用である。9月入学の最大のベネフィットは、日本の教育の国際化だろう。現在、高等教育機関に在籍している学生のうち、海外への留学者は 0.8%、受け入れは 3.5%にとどまっている[*14]。しかし、留学生が少ない理由について、過去の研究は、就職活動の早期化、言語力の低さ、教育機関同士での単位互換が行われないことなどを指摘しており[*15][*16]、「入学時期」が決定的な要因であるとの主張は多くない。本当に「国際化」を実現したいのなら、実践的な英語教育、国際交流プログラムや単位互換の推進、留学のための奨学金充実なども同時に着手すべきだということだろう。また、海外留学が将来の賃金を高めることを示す研究もあるが[*17]、海外で学位を取得した優れた人材が海外で就労する「頭脳流出」につながることを示した研究もある[*18]。
敢えて強調しておきたいのだが、私は大学の国際化のために9月入学を進める点には賛成である。しかし、18日の会合で早稲田大学の田中総長が指摘されたように、高校以下すべての学事暦を変えずとも、大学自体の入学時期と卒業時期を柔軟に設定することで十分に対応が可能である[*19]。「留学」と言ったときに、多くの人が想像するのはアメリカやイギリスなどの「欧米諸国」を思い浮かべるのであろうが、それ以外の国もある。オーストラリアやニュージーランドは9月ではなく2月入学であり、9月入学のみに縛ると 今度はオセアニア諸国への留学や、受け入れが難しくなる。そうではなくて、「入学時期と卒業時期を柔軟に設定する」ことで、すべての国への留学や受け入れを増やしていこうというのが田中総長の主張であり、私もこれに賛同する。

筆者の所属する慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスでは、既に9月入学や4学期制を実施しているから、現行の制度の下でも、大学の改革は十分に可能なのだ。日本全体でみれば、9月入学で留学しやすくなるという恩恵を受ける人の数は決して多いとは言えない上、それが経済全体にもたらすベネフィットが十分に大きいとも言えない中では、高校以下の学事暦をすべて変えるのではなく、大学の入学時期や卒業時期の柔軟化で「国際化」に対応すべきではないか。
9月入学を実施すれば、コスト削減効果が期待できる。高校入試や大学入試は例年1~2月に実施されている。この時期は降雪などの天候悪化、交通機関の乱れに加え、インフルエンザなどの感染症の流行が懸念される時期であるため、もし入試の実施時期を5~6月にずらせるのであれば、高校入試や大学入試にかかるコストを削減できる可能性は高い。その一方、9月入学という制度変更そのものにかかるコストは少なくない。一部報道では、移行期の 4~8月分も児童生徒は学校での学習を続ける前提で必要な学費や給食費などの家計負担は 3.9億円との試算[*20]や教員が 2.8万人不足との試算もある[*21]。ベネフィットとコストを比較した場合、コストを上回るベネフィットがあることが示されなければ、国民の納得を得るのは難しい。
日本の政策形成プロセスへの課題
最後に、日本の政策形成プロセスに対する課題を述べたい。経済学で体系化されている政策評価は、政策の「成果」と「手段」の因果関係を明らかにするために行われる。この時、手段は必ずしも1つとは限らない。期待された成果を達成するために考えうる手段は1つではないからだ。複数の手段がもたらす効果の大きさを比較し、もっとも費用対効果に優れた手段を選択すれば合理的である。しかし、政策の成果は何かということを議論することなく、手段だけが議論されることが多いのが問題である。また、このように整理してみると、「コロナの被害を受けた世代への対策」と、従前から議論されている「教育の国際化」は、まったく別の目的を持つ政策課題であり、同じ「9月入学」という手段で解決できないことは 明らかである。
期待された成果を達成するためには
ここまで整理してきた通り、今回のコロナウィルスによって生じた臨時休校がもたらした学力の低下や学力格差の解消を目的とするならば、9月入学以外にも、夏休みの短縮や土曜日の補修は検討されるべきオルタナティブだ。そして日本の国際化や入試コストの削減を目的とするのであれば、留学のための奨学金拡充や年に数回の大学入学資格試験の実施なども検討されるべきオルタナティブであろう。しかし、9月入学以外の議論が行われた形跡はなく、「9月入学」の是非のみが議論されている。9月入学ありきで議論するのではなく、期待された成果を達成するために何が必要とされるかを議論することこそ、広く国民の利益にかなうのではないか。
参考文献
[*1] Belot, M., & Webbink, D. (2010). Do teacher strikes harm educational attainment of students?. Labour, 24(4), 391-406.
[*2] Jaume, D., & Willén, A. (2019). The long-run effects of teacher strikes: evidence from Argentina. Journal of Labor Economics, 37(4), 1097-1139.
[*3] Marcotte, D. E. (2007). Schooling and test scores: A mother-natural experiment. Economics of Education Review, 26(5), 629-640.
[*4] Baker, M. (2013). Industrial actions in schools: strikes and student achievement. Canadian Journal of Economics, 46(3), 1014-1036.
[*5] Downey, D. B., Von Hippel, P. T., & Broh, B. A. (2004). Are schools the great equalizer? Cognitive inequality during the summer months and the school year. American Sociological Review, 69(5), 613-635.
[*6]読売新聞 5 月 4 日(https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20200501- OYT1T50180/)
[*7] Escueta, M., Nickow, A. J., Oreopoulos, P. & Quan, V., Upgrading Education with Technology: Insights from Experimental Research. Forthcoming in Journal of Economic Literature.
[*8] Cacault, M. P., Hildebrand, C., Laurent-Lucchetti, J., & Pellizzari, M. (2019). Distance Learning in Higher Education: Evidence from a Randomized Experiment.
[*9] Hansen, B. (2011). School year length and student performance: Quasi-experimental evidence. Available at SSRN 2269846.
[*10] Pischke, Jörn-Steffen. (2007). The Impact of Length of the School Year on Student Performance and Earnings: Evidence from the German Short School Years. Economic Journal 117 (523): 1216–42.
[*11] Park, R. J., Goodman, J., Hurwitz, M., & Smith, J. Heat and learning. American Economic Journal: Economic Policy.
[*12]文部科学省「公立学校施設における空調(冷房)列日の設置状況について」 (https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421285.htm)
[*13] Black, S. E., Devereux, P. J., & Salvanes, K. G. (2011). Too young to leave the nest? The effects of school starting age. The Review of Economics and Statistics, 93(2), 455-467.
[*14] 李嬋娟. (2019). 海外留学の効果に関する実証分析―(非) 認知能力と労働市場の成果を中心に ―. 明治学院大学国際学研究』(54), 1-28.
[*15] 小林明(2011)「大学における派遣留学の動機付け―日本人学生の海外留学阻害要因と今後の対 策―」『留学交流』2.
[*16] 太田浩(2014)「日本人学生の内向き志向に関する一考察 ―既存のデータによる国際志向性再 考―」『国際交流』40
[*17] Waibel, S., Ruger, H., Ette, A., and Sauer, L. (2017). Career consequences of transnational educational mobility: A systematic literature review. Educational Research Review, 20, 81-98
[*18] Parey, M., & Waldinger, F. (2011). Studying abroad and the effect on international labour market mobility: Evidence from the introduction of ERASMUS. The economic journal, 121(551), 194-222.
[*19] 早稲田大学総長 田中愛治「自由民主党秋季入学制度検討ワーキングチーム 2020 年 5 月 18 日 (月)ヒアリング 「9 月入学移行論」の目的と大義と必要な政策の方向性
[*20] 日本経済新聞 5 月 15 日 (https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59139340V10C20A5CE0000/)
【執筆:慶應義塾大学総合政策学部 中室牧子】






