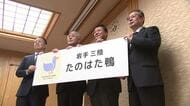11月9日の夕方に発生した三陸沖を震源とする地震は、最大震度4の揺れが観測され、岩手県には津波注意報が出されました。
その後も県内では三陸沖を震源とする震度1以上の地震が22回観測されていて、注意が必要な状況は続いています。
一方で9日の地震は地震の規模を示すマグニチュードが6.9と、マグニチュード7までには達しませんでした。
ここで注目されたものが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」です。
この情報を巡って気象庁では地震当日の会見で次のように説明しました。
気象庁 清本真司地震津波対策企画官
「北海道・三陸沖後発地震注意情報の対象地域ではあるが、地震の規模が発表対象となっていないので、北海道・三陸沖後発地震注意情報は発表対象となっていない」
この「後発地震注意情報」とは、3年前に運用が始まったものですが、今回はその対象となりませんでした。
ーーそれはどうしてなのか、またこの情報が出されたらどうしたらよいのか…。
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは、北海道から岩手沖の日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード7以上の地震が発生した場合、より大きな地震への注意を呼びかけるもので、気象庁などがおおむね2時間以内に発表します。
この震源域では過去の事例の分析をもとに巨大地震の発生が切迫しているとされています。
そして、このエリアではM7クラスの地震が発生した後、それに続く大きな地震=後発地震が発生した事例があります。
それが東日本大震災です。2011年3月9日にマグニチュード7.3の地震が発生しました。
その2日後の3月11日にマグニチュード9の超巨大地震が発生しています。
このことから、より大きな地震への注意を呼びかけ被害を最小限に抑えようと注意情報の運用が始まりました。
ただ今回は基準となるマグニチュード7に達しなかったため、注意情報は発表されませんでした。
発表される場合、対象地域はあらかじめ決まっています。
巨大地震が起きた場合、「3m以上の津波」や「震度6弱以上の揺れ」が想定される地域です。
県内では沿岸部だけでなく盛岡市から一関市までの内陸部を含む23の市町村が対象です。
ーー後発地震注意情報が出されたら何をすべきなのか…。
1回目の地震から1週間程度の間は「すぐに逃げられる状態で寝ること」「非常用品の常時携帯」「緊急情報を取得できるようにする」など災害への備えの再確認やすぐに避難できる態勢の準備が必要となります。
この後発地震注意情報に似たものとして「南海トラフ地震臨時情報」というものがあり、2024年の8月に関東から九州にかけて発表され、巨大な地震が発生した際、避難できる準備をするよう呼びかけられました。
気象庁では9日の地震について、1週間程度は同程度かそれ以上の地震に対して注意するよう呼びかけています。