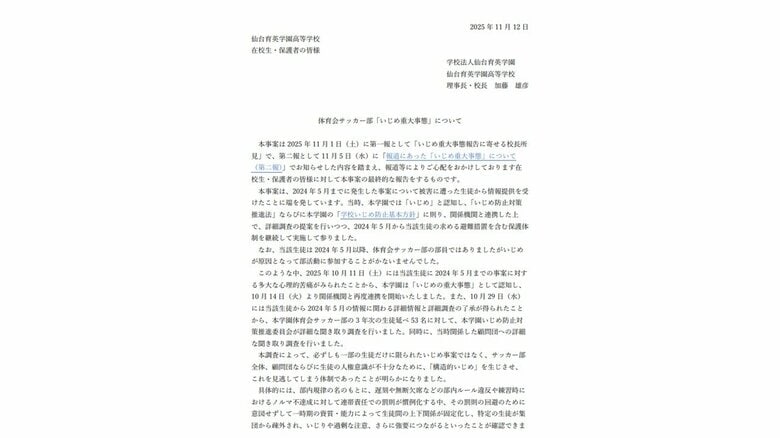仙台育英学園は11月12日午前、公式ホームページ上で、体育会サッカー部で発生した「いじめ重大事態」に関する報告を校長名にて発表した。
以下、学園が公表した文書の全文(原文のまま)。
体育会サッカー部「いじめ重大事態」について
本事案は 2025年11月1日(土)に第一報として「いじめ重大事態報告に寄せる校長所見」で、第二報として11月5日(水)に「報道にあった『いじめ重大事態』について(第二報)」でお知らせした内容を踏まえ、報道等によりご心配をおかけしております在校生・保護者の皆様に対して本事案の最終的な報告をするものです。
本事案は、2024年5月までに発生した事案について被害に遭った生徒から情報提供を受けたことに端を発しています。
当時、本学園では「いじめ」と認知し、「いじめ防止対策推進法」ならびに本学園の「学校いじめ防止基本方針」に則り、関係機関と連携した上で、詳細調査の提案を行いつつ、2024年5月から当該生徒の求める避難措置を含む保護体制を継続して実施して参りました。
なお、当該生徒は2024年5月以降、体育会サッカー部の部員ではありましたが、いじめが原因となって部活動に参加することがかないませんでした。
このような中、2025年10月11日(土)には当該生徒に2024年5月までの事案に対する多大な心理的苦痛がみられたことから、本学園は「いじめの重大事態」として認知し、10月14日(火)より関係機関と再度連携を開始いたしました。
また、10月29日(水)には当該生徒から 2024 年 5 月の情報に関わる詳細情報と詳細調査の了承が得られたことから、本学園体育会サッカー部の3年次の生徒延べ53名に対して、本学園いじめ防止対策推進委員会が詳細な聞き取り調査を行いました。
同時に、当時関係した顧問団への詳細な聞き取り調査を行いました。
「構造的いじめ」と認定
本調査によって、必ずしも一部の生徒だけに限られたいじめ事案ではなく、サッカー部全体、顧問団ならびに生徒の人権意識が不十分なために、「構造的いじめ」を生じさせ、これを見逃してしまう体制であったことが明らかになりました。
具体的には、部内規律の名のもとに、遅刻や無断欠席などの部内ルール違反や練習時におけるノルマ不達成に対して連帯責任での罰則が慣例化する中、その罰則の回避のために意図せずして一時期の資質・能力によって生徒間の上下関係が固定化し、特定の生徒が集団から疎外され、いじりや過剰な注意、さらに強要につながるといったことが確認できました。
本学園としてはこのような「構造的いじめ」を防止できず、被害に遭った生徒および保護者に多大な心理的苦痛をもたらしたことに深くお詫び申し上げます。
当該生徒が幼少期より大好きであったサッカーという競技を、本学園での課外活動により許しがたい競技とさせてしまったことは、教育に携わる機関として慙愧に堪えません。
今後もこの償いに誠心誠意尽くして参る所存です。
決勝戦出場とその後の対応
本学園としては、上記のいじめ事案の理解に至るまでの調査が第104回全国高校サッカー選手権大会宮城県予選の決勝戦前に完了しておらず、生徒の特定といった新たな人権侵害を生まないために、被害に遭った生徒・保護者に事情を説明した上で全部員での決勝戦出場ならびに観戦を認めた経緯があります。
しかしながら、調査によって確認できた内容を踏まえると、人権意識の適切かつ十分な理解が顧問団ならびに生徒になければ、今後も同様の事案発生が起こり得ると判断しております。
そのため、本学園は2025年12月末まで顧問団への人権意識の適切な理解を深める研修と、その顧問団が生徒一人ひとりと丁寧な二者面談を通じて人権意識を指導する時間を設けるために、
12月末まで体育会サッカー部の対外活動停止(12月28日から開催される第104回全国高校サッカー選手権大会を含む各大会への出場辞退および対外練習試合の中止)を行います。
これまで体育会サッカー部は活動を停止しておりましたが、今後はこの二者面談と併せて学内に限った練習を開始いたします。
全部活動に拡大した調査
さらに三者面談を通じて、本事案の「構造的いじめ」に関わる調査結果を体育会サッカー部の生徒ならびに保護者に説明を行い、本学園がこの「構造的いじめ」を認知し、事前に防止することができなかったことをお伝えしているところです。
そして構造的に不特定多数に対して加害行為を行い得る組織環境となっていることを認めた上で、とりわけ被害に遭った生徒および保護者の多大な心理的苦痛について説明しているところです。
さらに、第二報でお伝えしたとおり、学校法人仙台育英学園が設置する仙台育英学園高等学校、秀光中学校、仙台育英学園沖縄高等学校の全部活動の生徒延べ2000名以上に対して11月7日(金)に調査を開始いたしました。
「いじり」もいじめに該当し得ると明示
一般的に他者に対してからかう・冗談を言う・反応を楽しむといった軽いコミュニケーション行為を指す「いじり」であっても、
「相手が明確に不快・屈辱・恐怖・孤立を感じている」、「周囲の笑いのために特定の個人を繰り返し扱う」、「上下関係や集団圧力の中で抵抗できない状況で行われている」などに該当する場合は、
「いじり」を行った者の意図に関係なく、「いじり」を受けた者が傷つき、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」に該当することについて、改めて各生徒への自覚を促すとともに、
本学園のあらゆる部活動における「いじめ」有無に関し調査したものです。
この調査の結果を踏まえ、構造的な課題が発見された部活動についてはその課題の解決に注力するために今後さらに詳細調査を行う予定です。
なお、同調査に関わる体育会サッカー部の生徒からの回答には本事案を認識の上、「構造的いじめ」が存在していることを指摘し、強く反省している者もいることをご報告いたします。
学園の謝罪と再発防止策
本学園は教育機関としての責任を深く自覚し、被害に遭った生徒および保護者に深くお詫び申し上げるとともに、
当該生徒が安心・安全な学校生活を送ることができるよう、引き続き取り組んで参ります。
当該生徒がかつて好きであったサッカーという競技を再び楽しめる日が来るよう努めて参ります。
また、人権侵害を防止する観点のもとで生徒一人ひとりの尊厳を守り、安全で健全な学園生活を確保することを最優先課題とし、信頼回復に全力を尽くして参ります。
なお、今回の体育会サッカー部の対外試合停止および人権保護の啓蒙活動にあるとおり、
本学園の「いじめは人間として絶対に許されない」(「学校いじめ防止基本方針」)という姿勢に変わりはありません。
※文中の改行・段落構成のみ編集。本文は原文のまま掲載。