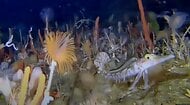海と聞くとプランクトンがたくさんいて…というイメージがあるかもしれないが、実はプランクトンが豊富にいるのは沿岸部周辺だけで、沖合は、プランクトンが少ない砂漠のような海域が広がっている。

南極大陸を取り巻く南大洋の広大な海域は、窒素やリンなどの栄養塩といったプランクトンに必要な成分が豊富にあるにもかかわらずプランクトンが少ない。南大洋にはミネラルである「鉄」が欠乏していることが関係していると考えられている。

南アメリカのパタゴニアやオーストラリアなどの乾燥地域の鉄分を含んだ鉱物粒子が風により舞い上がり、はるばる南大洋に飛来して海に落ちると、じわじわと鉄が溶け出す。海の鉄成分はこうして大気を経由して供給されるという。
つまり“皮肉なことに”地球温暖化で陸が砂漠化すると、海が豊かになるという仮説があるのだ。
大陸からの微粒子を採取して海へのミネラル供給メカニズムを調査
この仮説の解明に挑もうとしているのが、山梨大学の小林拓さん。
第64次南極地域観測隊で、南極観測船しらせの船上において大陸から飛来した微粒子(大気エアロゾル)を採取するなどして海にミネラルが供給されるメカニズムを解き明かそうとしている。

その一つが、偏光光散乱式粒子計測器を使用する調査方法。
小林さんが自作で作った装置で、ポンプで外の空気を吸い込み、レーザー光を当て微粒子がキラキラする様子から鉱物粒子の量を調べる。

もう一つが、船舶用オリオールメータ。
これは、海面付近ではなく大気全体の粒子の様子を知るために、大気エアロゾルが太陽光をキラキラと散乱させた光の量を測定する装置で、光冠(オリオール)と呼ばれる太陽の周りの輝きを測る装置だ。

太陽を描くとき、世界中の誰もが、丸い円の周りに、放射状の線をたくさん描くのではないだろうか。実際人間の目には、太陽の周りが輝いて見え、太陽から光線が出ているように見えるからだ。

これは、空に舞い上がっている大気エアロゾルが光を散乱すると見えるためで、空が澄んで粒子がない場所で太陽を見ると、太陽の周りの線は見えなくなるという。
船舶用オリオールメータは、太陽の周りの輝き具合を調べることで、大気中に浮遊する微粒子の性質や量を計測している。
海の大半が砂漠のような状況だといわれるなか、研究成果によって、より豊かな海の実現も将来訪れるかもしれない。
〈小林拓さん〉
山梨大学 生命環境学部 環境科学科/大学院総合研究部 生命環境学専攻 衛星リモートセンシング、沿岸海域の汚濁、エアロゾル、光を利用した測定器開発